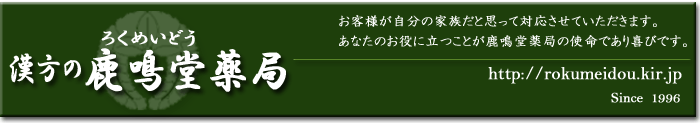 |
||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||
| がん患者さんの家族 | 患者さんにケアを提供する家族 | 第二の患者としての家族 | 心の専門家へのご相談 | |||||||||||||||
| 1.がん患者さんの家族 | ||||||||||||||||||
患者さんががんと告げられると、家族全体に大きな変化が生じます。それらの変化は精神的な面だけではなく、患者さんの身の回りの世話などの現実的な問題、家族の役割の変化、経済的な問題など幅広いものです。このような意味で、がんは「家族の病」ともいわれています。また欧米では1970年代以降、がんが家族に与える精神的負担(不安、落ち込み、など)に関する研究が行われてきました。その結果、家族も患者さんと同程度、またはそれ以上の精神的負担があることが報告されています。さらに家族の精神的負担は、患者さんの精神状態にも影響します。 一般に患者さんの家族には、2つの側面があるといわれています。1つは患者さんにケア(情緒的支援、経済的支援、意思決定の責任の共有、など)を提供する側面であり、もう1つは「第2の患者」として精神的ケアを必要とする側面です。実際の医療の現場では、家族は患者ケアの提供者として扱われることが多く、家族のケアは後回しになっています。 |
||||||||||||||||||
| 2.患者さんにケアを提供する家族 | ||||||||||||||||||
家族ができる患者さんへの心のケアを箇条書きしました。参考にしてみてください。
1)患者さんの気持ちを理解・共有する
患者さんの気持ちを理解して共有することは、家族にしかできないかけがえのない役割の1つです。気持ちを理解し共有するためには、口をはさみたくなっても少し堪えて、患者さんの話に耳を傾けることです。自分の意見をいう前に、患者さんの話に黙って耳を傾ける態度が大切です。
2)率直に語り合う
患者さんが心配していることは何か、将来の計画をどうしていきたいと考えているかなどを率直に話し合い、患者さんの意思を尊重するために、家族として何ができるかを考えてみましょう。患者さんが話を避けるのでない限り、病気や死に関する話題について、家族から「そんなこといわずに・・・」などと不自然に避けないことも大切です。
3)「がんばれ」と励ましすぎない
患者さんががんばり続けて心が疲れているときに、家族から「がんばれ」という言葉をかけられると「これ以上何をがんばればいいのか」という気持ちになることがあります。患者さんから「つらい」という言葉が聞かれると、家族は力づけようと「そんなこといわずにがんばろうよ」と返答しがちですが、「そんな風に思うほどつらかったんだね」といういたわりの言葉が、ときに患者さんにとって安心感につながります。
4)これまでどおりに接する
患者さんによっては、病気をきっかけに特別扱いされることで、家族の中で孤立感を深める場合があります。担当医に、現在の身体状態で何ができて何ができないのかを確認したうえで、患者さんができることやしたいことを尊重し、家族は必要に応じてサポートをすることも大切です。
5)患者さんの対処法を尊重する
ストレスに対する患者さん自身の対処法を尊重しましょう。ときには、患者さんの気持ちや行動が、家族にとって理解しにくいことがあります。例えば、まるでがんではないように振舞ったり、子供返りをしたり、家族に対して普段からいらだった態度を見せたりする場合です。このような行動の背景には、自分にとって、受け入れがたい出来事に対して湧き上がるさまざまな感情を処理するため、無意識のうちに心の対処機能が働いていることが考えられます。これらは、ストレスに対する必要な対処です。例えば、がんではないと考えて必要な治療を受けないなど、患者さん本人にとって不利益がない限り、温かく見守る姿勢も必要です。
|
||||||||||||||||||
| 3.「第2の患者」としての家族 | ||||||||||||||||||
家族は、患者さんをケアする役割に没頭して、自分自身の心のケアを怠りがちです。また患者さんの精神的な支えになるために、自分のつらい気持ちを心の奥底にしまい込んで、気丈に振舞うことが多いようです。
さらに、患者さんに心配をかけることへの気づかいから、心の専門家への相談をためらいがちです。まずは、自分自身のつらさを認めることが大切です。 1)家族の感情とその対処
患者さんががんと告げられたときから、家族にさまざまな感情(動揺、怒り、自責感、不安、落ち込み、など)が生じます。家族は、自分の感情の変化に戸惑いを感じることがありますが、そのような変化は一般的にみられる通常の反応で、異常な反応ではありません。
また、家族に生じる感情にはいくつかの対処方法があります。有効な対処方法は人によって異なり、一般的には、その人が過去の困難な問題に対して成功した対処方法が有効であるとされています。 以下の項を参考にしてください。 がんと上手につきあうための工夫 1.動揺(ショックで混乱する)
悪い知らせの後には一時的に動揺しますが、時間とともに軽減します。注意力の低下による失敗を減らす工夫(必要なこと以外は先延ばしする、患者さんや他の家族と情報を整理して共有する、など)をすることも大切です。
2.怒り(いらいらする)
悪い知らせの後の怒りは当然の反応ですが、周囲の人につらく当たってしまい、その対処に戸惑うこともあります。人前では自分の伝えたいことを感情的にならずに適切に主張し、怒りを自分の中にため込まないことも大切です。また、身近な人に相談したり、日記をつけたりして自分の感情を表現することも対処方法の1つです。
3.自責感(自分が悪かったのではと考える)
家族がしたことやしなかったことが、患者さんのがんの原因とはいえません。過去を振り返って自分を責めないようにすることが必要です。
4.不安
不安の症状については、以下の項を参考にしてください。
がん患者さんが経験する心の状態−不安と落ち込み(抑うつ)− がんの病状や治療だけでなく、将来に対するさまざまな不安が生じます。正しい情報を集めて整理することで、不必要な不安を取り除くことができます。また意識的に気晴らしをして、自分の注意を患者さんや治療以外に向けることも大切です。 ※不安が対処できずに、いらいらしたり眠れない状態が2週間以上持続し、生活に支障をきたす場合には、心の専門家にご相談ください。 5.落ち込み(抑うつ)
落ち込み(抑うつ)の症状については、以下の項を参考にしてください。
がん患者さんが経験する心の状態−不安と落ち込み(抑うつ)− 落ち込みは当然の反応です。無理に前向きになろうとする必要はありません。気持ちを周囲の人に聞いてもらうことも助けになります。無理に自分を励ましてがんばったり、落ち込みを当たり前のこととしてそのままにしておくことで、症状が長引くこともあります。 ※一日中気分の落ち込みが続く状態が2週間以上持続し、生活に支障をきたす場合には、心の専門家にご相談ください。 2)家族の感情の変化
家族の感情の変化は、以下に示すように患者さんのがん治療経過に影響を受けます。また、家族特有のストレスもあります。
1.急性期(診断、再発などの悪い知らせの後)
家族はその悪い知らせを否定したり、怒りや不安を感じます。このような悪い知らせの後の家族の反応は、患者さんががんを告げられたときと同じ経過をたどります。
以下の項をご参考にしてください。 がんに伴う一般的な心の動き 2.慢性期(治療中や治療後の療養期間)
患者さんと家族の意見が一致しないことへの不満や、患者さんのために、家族がこれまでの日常生活が妨げられ、犠牲になったという負担感などが高まり、怒り、落ち込みといった感情が生じることがあります。
また、親戚や友人に患者さんががんであることを告げられない場合は、周囲からのサポートが得られずに孤立し、気分の落ち込みが強まることがあります。 3.終末期(緩和ケア期間)
終末期患者さんの痛み、倦怠感といった身体症状に対して、家族は自分が援助できないことで、無力感や気分の落ち込みを感じることがあります。また、せん妄(身体症状などによる意識障害)によって家族間のコミュニケーションが妨げられたり、家族に意思決定の責任が委ねられることで、家族の負担や不安が強まることがあります。さらに終末期患者さんの病状や予後に関しては、悪い知らせを家族だけが伝えられている場合もあります(注)。このような場合は、特に家族の不安や気分の落ち込みが強まることがあります。
(注)現在がんに関する悪い知らせは、患者さん本人に伝えることが一般的となっています。 4.死別後
亡くなった家族のことを考えると悲しくて涙が出る、もっとこうすればよかったと後悔したり、自責感を感じる、何もする気がせずにぼーっとしている、亡くなった家族の思い出の場所や物に気持ちが引き込まれる、外に出たくない、といった反応は死別による悲嘆反応です。また悲嘆反応は折にふれて(命日や故人ゆかりの記念日など)強く現れます。悲しみ、落ち込み、孤独感などは正常な反応で、異常な反応ではありません。悲嘆反応の強さや持続する期間は、看取りの状況、家族の関係など、さまざまな要因によって個人差があります。一般的には、死別後約1年で徐々につらさが和らぎ始めますが、現実を認めて故人のいない世界に適応するまで数年を要する方もいます。
|
||||||||||||||||||
| 4.心の専門家へのご相談 | ||||||||||||||||||
上記のようなつらい感情が持続し、生活への支障を生じている場合は、家族の精神的負担になります。家族自身の対処によって精神的負担が軽減されない場合、心の専門家(精神科医、カウンセラー)に相談して精神的ケアを受けることをおすすめします。
相談するタイミングは、以下を目安にしてください。
以下の項を参考にしてください。
自分の気持ちについて振り返る また、以下のような場合は、家族の精神的負担が強まる可能性があります。
|
||||||||||||||||||
| ※このページのコンテンツ内容は国立がんセンターがん対策情報センターから転用させていただいています。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||